『空海の風景』を読んで
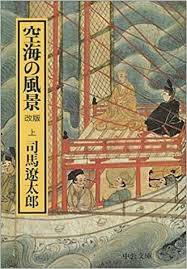
『空海の風景』を読んで (以下の内容はLINEのタイムラインに投稿して、(全く)反響が無かった内容を再編集し投稿した。) 初めに ひさびさの読書感想文だ。 前回の『アンナ・カレーニナ』以来の、約一年半振りである。 その間に何も読んで無かった訳では無い。 書籍では『最後の将軍 -徳川慶喜-』、漫画では『軍鶏』『トライガン(マキシマム)』『頭文字D』等、色々と読んでいた。 しかし一番読んだのは『空海の風景』だろう。 司馬遼太郎作品であるのに読むのに難渋した為、四度も読んだ。 ざっと作品を説明すると、弘法大師・空海の故郷から始まり、生い立ち、幼年期、青年期、唐に渡り帰国後の最澄との衝突・軋轢等が描かれている。 仏教の用語をなるべく使わずに書いた、と後書にある様に、別に仏教に詳しく無くても読める作品だ。 しかし、四度も読んでもハッキリとイメージ出来なかった。 作品世界の可視化 私は司馬好きではあるが別に文学好きでは無いので的を射ているか不安だが、司馬作品の特徴として挙げられるのは、小説舞台の可視化だ。 かつて何かの作品の後書でも見たし、人からも聞いた事が有るが、司馬さんが新たに新聞連載を始める前に神田古書街から特定の時代・ジャンルの本が消える為、彼が次にどういう作品を書くか大体予想が付いたそうだ。 なるべく史実に沿った作品を書く、と言うのも目的に有るだろうが、その時代、その地域、その世界を著者自身の頭の中にほぼ完璧に再現する為では無いだろうか。 そうでなければ、特に文学好きなわけでも無い私のような人間が好んで読まないし、読めるべくも無い。 メジャーどころだと元亀・天正の頃か幕末・維新の頃が舞台になる事が多いが、当時の世界が細かく描かれている為にイメージしやすいのだ。 その、読み易いハズの司馬作品であるのに、四度も読んだ。 前回の『アンナ・カレーニナ』と同じく、知らない世界だったからだ。 要するに、奈良時代や仏教や唐についての知識や理解が不足していたワケだ。 その為最初...